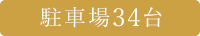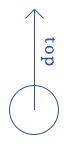ピロリ菌とは
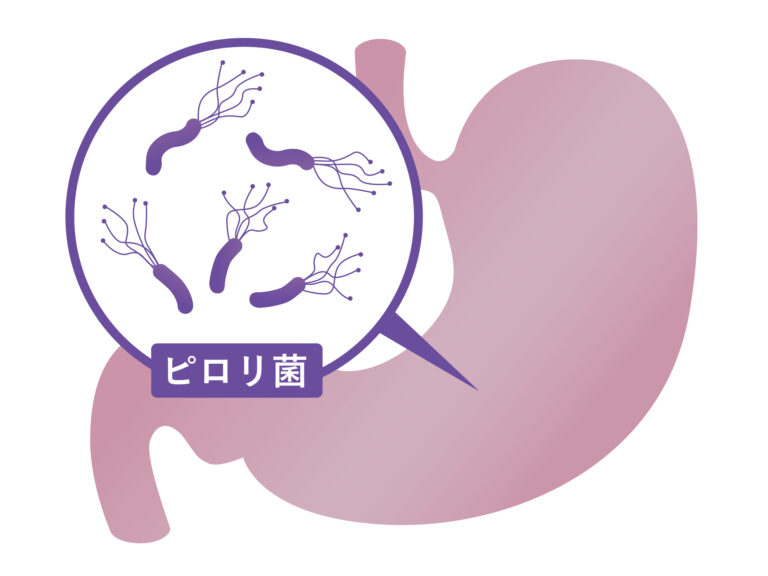
ピロリ菌(Helicobacter pylori、H. pylori)は、胃の粘膜に感染する細菌で、全世界で広く見られます。この細菌は特に胃の厳しい酸性環境に適応しており、胃の粘液層に生息して胃壁を攻撃することで様々な胃疾患を引き起こします。
ピロリ菌に感染するとどうなる?
ピロリ菌の感染は胃痛や胃の不快感などの症状を起こすことがあります。また慢性胃炎をはじめとした以下の疾患を引き起こすことがあります。
1. 慢性胃炎
ピロリ菌は慢性胃炎の最も一般的な原因です。感染すると、胃の内壁に炎症が生じ続けることで、萎縮性胃炎という状態がつづき、さまざまな消化不良症状が引き起こされます。
2. 胃潰瘍および十二指腸潰瘍
ピロリ菌は、胃または十二指腸の壁の損傷を助長します。胃壁を保護する粘液の産生を阻害し、胃酸が直接壁に作用しやすくなるため、潰瘍が形成されます。この結果、激しい腹痛、胃部不快感、食後の痛み、胃痛などが生じます。
3. 胃癌
ピロリ菌感染は、胃癌発生のリスクを高めることが広く知られています。胃がんの98%がピロリ菌が原因ともいわれています。特に、慢性胃炎が長期にわたって進行すると、胃癌になる確率が上がっていきます。胃がんのリスクは感染が長期間にわたるほど、また感染が早期に始まるほど高くなります。
4. リンパ腫
MALTomaと呼ばれる胃のリンパ腫(MALTリンパ腫)は、ピロリ菌による慢性的な刺激が原因で発症します。
5. その他の疾患
ピロリ菌は、特発性血小板減少症などを起こすとされています。
ピロリ菌の歴史
胃の中は強力な塩酸により酸性環境になっているため、細菌の生息はありえないと考えられていました。ピロリ菌の発見は、オーストラリアの医師であるバリー・マーシャルと病理学者のロビン・ウォーレンによってなされました。マーシャルは1984年に自ら細菌の懸濁液を飲む実験を行い、健康な胃にも細菌が感染し、急速に胃炎を引き起こすことを実証しました。
ピロリ菌はなぜ胃の中で生き残れるのか?
ピロリ菌は胃酸の厳しい環境で生存するために、尿素酵素(ウレアーゼ)を産生します。この酵素は尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解し、生成されたアンモニアが周囲の酸を中和し、細菌自身が生き残れるような環境を作り出しています。
ピロリ菌はどのように感染するのか
ピロリ菌感染は主に幼少期に起こるといわれています。
ピロリ菌の感染経路は、結論がでていませんが、ピロリ菌は土壌にも自然に生息しており、以下のような感染経路が考えられています。
- 井戸水、湧き水
- 感染している大人から乳幼児への口移し
ATTENTION以下のような方はピロリ菌を調べましょう
ピロリ菌は幼少期に感染が成立すると考えられており、成人になってからの感染はまれとされています。
- 両親や祖父母がピロリ菌と診断された。
- 両親や祖父母が胃がんである。
- 自宅が井戸水を使用している(していた)。
ピロリ菌に感染をし、感染している期間が長ければ長いほど発癌のリスクが高くなりますので、なるべく若い年齢のうちに一度検査を受けることをお勧めします。
ピロリ菌の検査方法
 ピロリ菌の検査は、基本的には胃カメラ検査を行い、ピロリ菌の感染を疑う胃炎や潰瘍、胃がんなど認めた場合、保険適用されます。
ピロリ菌の検査は、基本的には胃カメラ検査を行い、ピロリ菌の感染を疑う胃炎や潰瘍、胃がんなど認めた場合、保険適用されます。
以下のような方は保険で検査ができます。
- 内視鏡検査または造影剤を用いたX線検査で胃潰瘍または十二指腸潰瘍と診断された
- 胃MALTリンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病の診断を受けた
- 早期胃がんに対する内視鏡の治療を受けた
- 胃カメラで胃炎と診断された
ピロリ菌検査を保険適用で受けるためには、胃カメラを受ける必要があります。半年以内に受けた胃カメラで上記の診断を受けた場合は、その診断が有効とされて保険適用されます。なお、当院以外で受けた半年以内の胃カメラの場合も、診断結果をご持参いただければ保険適用となります。
胃カメラ
胃カメラで組織を採取して調べる検査と、胃カメラを使わない検査に分けられ、それぞれ複数の検査法があります。
胃カメラで組織を採取して行う検査
胃カメラは、食道・胃・十二指腸粘膜の精密な観察に加え、止血などの処置や組織採取が可能な検査です。採取した組織は病理検査で多くの疾患の確定診断が可能になる他に、ピロリ菌感染の有無を調べるためにも使われます。胃カメラによる組織採取で行うピロリ菌感染検査には、迅速ウレアーゼ試験、検鏡法、培養法があります。
迅速ウレアーゼ試験
ピロリ菌はウレアーゼという酵素を用いて周囲の尿素からアンモニアを産生し、周囲を中和しています。この働きを利用してピロリ菌の有無を確かめる検査です。
検鏡法
採取した組織を顕微鏡で観察し、ピロリ菌の有無を確かめます。
培養法
採取した組織を培養してピロリ菌感染の有無を調べます。薬剤耐性のチェックなど、より精密な検査も可能になります。
胃カメラを使わない方法
血液や尿を用いる抗体検査、吐く息を採取して行う尿素呼気試験、便を調べる便中抗原検査に分けられます。
抗体検査
血液や尿を採取してピロリ菌に対する抗体の有無を調べる検査です。除菌に成功しても長期間陽性となってしまう検査であることから、除菌治療の成功判定には使われることがありません。
尿素呼気試験
特殊な薬を服用する前と後の呼気(吐く息)を採取して、ピロリ菌感染の有無を調べます。胃カメラを用いない検査の中では精度が高く、除菌治療の判定検査として行われることが多くなっています。
便中抗原検査
採取した便にピロリ菌抗原が存在するかどうかを調べる検査です。
ピロリ菌感染の有無を調べる場合、そして除菌治療の成功判定をする場合、上記の検査を行います。複数の検査を組み合わせて診断することもあります。
ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌の感染が確認されたら除菌治療が必要です。
使用する薬剤
除菌治療は2種類の抗菌薬と、その効果を高める胃酸分泌阻害薬(プロトンポンプ阻害剤)を1日2回、7日間内服します。
除菌判定
除菌の効果を正確に調べるためには、1ヵ月ほど期間をおいてから判定検査を行う必要があります。除菌ができたかどうかは一般的に尿素呼気試験か便抗原検査を行います。
除菌判定は必ず受けましょう。
ピロリ菌には薬剤がききにくいものが存在します。初回の1次除菌の成功率は約90%とされています。失敗した場合には、抗菌薬を1種類変更してあとは同様の2次除菌が可能です。
除菌治療の副作用
なお、除菌治療では、下痢・軟便・味覚異常・肝障害やアレルギー反応といった副作用が生じる可能性があります。また、胃粘膜の状態が改善することで逆流性食道炎を起こし、胸やけなどの症状を起こすことがありますが、ほとんどの場合は自然に緩和していきます。
ピロリ菌3次除菌
ピロリ菌の除菌成功率は約9割程度と高いですが、患者様によっては1次除菌、2次除菌ともにうまくいかない場合があります。除菌が失敗する原因はピロリ菌が薬に対して耐性を持ってしまうことが考えられます。
ピロリ菌の3次除菌は保険適応の治療がなく、治療を断念されてしまう方もみえますが、一部の医療機関では1次除菌や2次除菌と抗生剤の種類などを変更し、自費診療として3次除菌を行っている施設があります。
当院でも、1次除菌・2次除菌の加えて、保険外診療の3次除菌にも対応しておりますので、気になる方は一度ご相談ください。
POINT当院での3次除菌について
対象となる方
- ピロリ菌1次除菌・2次除菌が不成功だった方
除菌の流れ
1.除菌治療前の検査
はじめにピロリ菌感染を確認するため、尿素呼気検査を用いて判定します。
はじめにピロリ菌感染を確認するため、尿素呼気検査を用いて判定します。
2.除菌治療
- ボノプラザン
- アモキシシリンorメトロニダゾール
- シタフロキサシン
この3種類の薬を1日2回の7日間内服していただきます。
3次除菌では約7~9割の方が除菌に成功します。
3.除菌治療後の評価
治療薬を内服終了後1~2か月後に尿素呼気検査で除菌が成功したかどうかの評価を行います。
治療の副作用
除菌治療に処方される3種類の薬の内の2種類が抗生剤なので、ピロリ菌の除菌治療では副作用が現れやすいと言われています。
主な症状は、下痢や軟便ですが味覚障害などの副作用もあらわれます。その他に、肝機能障害も確認されています。副作用の症状は軽いものが多く、治療を完遂できる方がほとんどです。痒みや発疹、発熱などのアレルギー反応があらわれた場合には注意が必要ですので、すぐに医師や薬剤師にご相談ください。
1.軟便、軽い下痢などの消化器症状や味覚異常が起きた場合
自己判断で服薬を止めてしまったり、量を変更したりせず、最後まで服薬してください。
下痢や味覚異常の症状がかなり悪化した場合は迷わずご相談ください。
2.発熱や腹痛を伴う下痢、下痢に粘液や血液が混ざっている場合、または発疹の場合
すぐに薬を飲むのを中断し、医師か薬剤師にご相談ください。
FEE除菌治療の料金
3次除菌は診察、検査、処方箋代、薬代のすべてが保険適用外で全額自己負担になります。
| 診察料(検査込み) | 11,000円 |
|---|---|
| 薬代 | 約7000円~9000円 (ジェネリック医薬品使用などにより前後します。) |
| 除菌判定(4~8週後) | - |
| 尿素呼気検査(便中抗原検査) | 6,600円 |
| 合計 | 約24,600~26,600円 |
アレルギーでピロリ菌の除菌ができない方
主にペニシリンやセフェム系抗生物質にアレルギーがある方は保険診療での除菌治療ができない場合があります。保険診療での除菌薬は必ずアモキシシリンという薬が入っているためです。抗生剤の種類を変更して除菌を試みることができますが、保険適応になっていないため、自費診療になります。
当院では、薬剤アレルギーで除菌が行えなかった方の保険外診療・ピロリ菌除菌治療に対応しております。ペニシリン抗生物質を使用せずほかのお薬を使用して除菌することになりますが、一般的なピロリ菌除菌治療のお薬と同じくらいの高い除菌効果がありますので安心して除菌治療を受けていただけます。
治療には、PPI(プロトンポンプヒビター)という胃酸の分泌を抑える薬と、ペニシリンが使用されていない抗生物質2種類を合わせて処方します。
抗生剤の種類や組み合わせは様々ありますが、ペニシリンやその他の薬剤アレルギーがある方、お腹が弱く下痢気味の方など、患者さま一人ひとりに適したお薬を処方するため、消化器疾患の専門医である院長が慎重に対応いたします。
治療の流れや費用については3次除菌の内容と同様となります。
ピロリ菌が心配になったら
 ピロリ菌が心配になったらピロリ菌は除菌治療が早ければ早いほどいいとされています。治療は内服治療を行いますが、ただしく治療をしないと除菌がうまくいかなかったり、薬に耐性をもってしまい、除菌ができなくなったりすることがあります。専門的な医療機関でしっかりとした診断と治療を受けましょう。
ピロリ菌が心配になったらピロリ菌は除菌治療が早ければ早いほどいいとされています。治療は内服治療を行いますが、ただしく治療をしないと除菌がうまくいかなかったり、薬に耐性をもってしまい、除菌ができなくなったりすることがあります。専門的な医療機関でしっかりとした診断と治療を受けましょう。
当院は日本ヘリコバクター学会認定のH.pylori感染症認定医が診療にあたっています。治療内容や副作用とその対処法なども含め、わかりやすく丁寧にご説明しています。なんでもお気軽にご相談ください。
文責:東海内科・内視鏡クリニック岐阜各務原院 院長 神谷友康