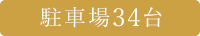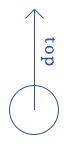過敏性腸症候群について
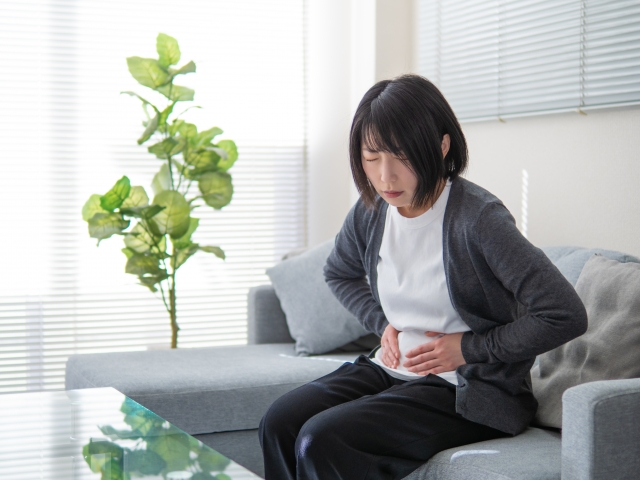 日常的に起こる腹痛や、下痢、腹部の不快感などを起こす方で、大腸検査などの検査を行い特に目に見える病気が見つからない方は、過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome, IBS)と考えられます。
日常的に起こる腹痛や、下痢、腹部の不快感などを起こす方で、大腸検査などの検査を行い特に目に見える病気が見つからない方は、過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome, IBS)と考えられます。
過敏性腸症候群は慢性的な胃腸の機能障害で、繰り返し発生する腹痛や腹部の不快感と、排便習慣の変化(便秘、下痢、またはその両方)が特徴です。過敏性腸症候群は検査上は、腸に明確な異常が見られないにも関わらず、症状が現れます。おなかが弱い、緊張をするとすぐ下痢をする、ストレスを感じると便秘しやすいなど、これまで体質とされていた症状は、ここ近年、過敏性腸症候群として診断されるようになりました。
大腸検査では異常はみつかりません。
過敏性腸症候群は、大腸粘膜に炎症や腫瘍などの器質的な異常はありませんが、知覚過敏や機能不全などによって腹痛を伴う下痢や便秘などの慢性的な症状を起こす病気です。一般的に大腸の機能が亢進すると下痢になり、低下すると便秘になりますが、過敏性腸症候群では強い亢進や低下を起こしやすく、その状態が長期間続きます。また、睡眠中に症状を起こすことがないというのは、大きな特徴になっています。
過敏性腸症候群の原因は・・・?
原因は医学的に明確にはなっていません。
しかし、腸の機能は自律神経がコントロールしていることから、緊張や不安をはじめとしたストレスの影響を受けやすい傾向があり、過敏性腸症候群でもストレスをきっかけに症状が現れることがよくあります。また、腸と脳は互いに影響を及ぼし合っている脳腸相関にあり、自律神経以外の内分泌なども相互に関与していることがわかっています。
過敏性腸症候群は若い世代の発症が増加傾向にあります。命に直接かかわる病気ではありませんが、学業や仕事に大きな悪影響を及ぼす可能性がありますので、疑わしい症状がある場合には早めにご相談ください。まずは大腸カメラ検査で他の病気が隠れていないかを確認することが重要です。
セルフチェック - このようなお悩みはありませんか?
- チェックはこちらから
- 前兆なく急に強い腹痛を起こし、激しい下痢になる
- 通勤・通学で途中下車し、トイレに駆け込むことがある
- 大事な会議やプレゼン、面接、試験中に腹痛を起こし、トイレに行くことがある
- 不安や緊張でおなかを壊すことがある
- 硬くて小さくウサギの糞のような便が出る
- 強くいきんでも便がほとんど出ず、残便感がある
- 緊張するとおならが出てしまうことがある
- 旅行でもトイレの場所が気になってしまう
- 就寝中には腹痛などの症状を起こすことはない
- 下痢や便秘などの便通異常が1か月以上続く
上記の症状がある場合、過敏性腸症候群が疑われます。気になる症状がありましたら、早めにご相談ください。
過敏性腸症候群の分類
主な症状は、腹痛を伴う下痢や便秘といった便通異常であり、それ以外にも膨満感などの症状を起こすタイプもあります。症状の内容によって下記の4種類に分けられますが、別のタイプに移行するケースもあります。
- 下痢型過敏性腸症候群
急に強い腹痛を起こし、トイレに駆け込むと水のような激しい下痢になり、排便後は症状がおさまります。
こうした症状を1日に何度も起こすこともあります。男性の発症が多く、通勤や通学でトイレに間に合わないのではと不安になり、そのストレスで症状を起こすという悪循環を起こしやすく、外出が苦手になることもあります。学業や仕事をはじめ生活全体に悪影響を及ぼす可能性がありますので、早めにご相談ください。
- 便秘型過敏性腸症候群
便が停滞して腹痛を起こし、強くいきんでも少量の便しか出ず、残便感があるといった症状を起こします。
便秘型は女性に多く、ウサギの糞のような小さくて硬くコロコロした便が少量しか出ない場合には、便秘型の過敏性腸症候群が強く疑われます。強く長くいきむ癖がついてしまうといぼ痔や切れ痔の発症・再発リスクも上がってしまいますので、注意が必要です。
- 交代型過敏性腸症候群
激しい腹痛を伴う便秘と下痢を繰り返します。長く便秘が続いた後で下痢になって再び便秘になる、下痢が続くが便秘になる時期もあるなど、様々なパターンで下痢と便秘を繰り返します。
- 分類不能型
膨満感、おなかが鳴る(腹鳴)、無意識におならが漏れるなど、便通異常以外の症状を起こすタイプです。
過敏性腸症候群を起こしやすい方
IBSの正確な原因はまだ完全には理解されていませんが、以下のような要因が関連していると考えられています。
- 腸の運動性の異常
腸の収縮が強すぎるか弱すぎると、それぞれ下痢や便秘を引き起こす可能性があります。 - 中枢神経系との連携の問題
腸と脳の間の通信障害が、過敏性を引き起こす可能性があります。 - 感染症後の変化
重度の胃腸感染症を経験した後にIBSの症状が発生することがあります。 - 腸内フローラの変化
腸内細菌の組成がIBS患者で異なる場合があります。 - 食事
特定の食品(乳製品、グルテン、高FODMAP食品など)が症状を悪化させる可能性があります。 - ストレス
ストレスや心理的な要因が症状を引き起こすか、悪化させる可能性があります。
FODMAP食とは
FODMAPは、消化や吸収が不完全であり、過敏性腸症候群(IBS)などの機能性胃腸疾患を持つ人々において腸内で過度の発酵を引き起こし、ガスの生成、腹痛、膨満感、下痢、または便秘などの症状を誘発する可能性のある一連の炭水化物です。FODMAPは以下の各項目の頭文字を取ったものです。
- Fermentable(発酵性の):腸内細菌によって発酵されやすい
- Oligosaccharides(オリゴ糖):フルクタン(小麦、ライ麦、玉ねぎなどに含まれる)やガラクトオリゴ糖(豆類に含まれる)など
- Disaccharides(二糖類):乳糖(乳製品に含まれる)
- Monosaccharides(単糖類):過剰なフルクトース(ハチミツ、リンゴ、高フルクトースコーンシロップなどに含まれる)
- And(および)
- Polyols(糖アルコール):ソルビトールやマンニトール(一部の果物や人工甘味料に含まれる)
これらの成分は、消化や吸収が不十分で、過敏性腸症候群(IBS)などの機能性胃腸疾患の人において腸内で発酵し、ガスを生成したり、水分を引き寄せたりすることで、腸内の不快感、膨満感、ガス、下痢、または便秘などの症状を引き起こす可能性があります。
過敏性腸症候群(IBS)の症状がある方は、一度これらの食事を制限をしてみてください。ご自身の身体に合わない食材が原因で下痢や腹部膨満感を起こしている可能性があります。
高FODMAP食品(避けるべき食品)
- 果物: りんご、梨、マンゴー、スイカ、桃、アボカド
- 野菜: アスパラガス、カリフラワー、にんにく、玉ねぎ、ねぎの白い部分、アーティチョーク
- 豆類: レンズ豆、ひよこ豆、黒豆、キドニービーンズ
- 乳製品: 牛乳、ヨーグルト、ソフトチーズ(これらは乳糖を含むため)
- 穀物: 小麦、ライ麦(パン、パスタ、シリアルなど)
- 甘味料: ハイフルクトースコーンシロップ、ソルビトール、マンニトール、キシリトール(一部のガムやキャンディーに含まれる)
低FODMAP食品(推奨される食品)
- 果物: バナナ、ブルーベリー、キウイ、オレンジ、イチゴ
- 野菜: キュウリ、レタス、トマト、ほうれん草、ジャガイモ、ニンジン
- タンパク質源: 肉、魚、鶏肉、卵、豆腐
- 乳製品代替品: ラクトースフリー製品、アーモンドミルク、ライスミルク
- 穀物: グルテンフリー穀物、米、キヌア、オーツ麦
- ナッツ: アーモンド(小量)、マカダミアナッツ、くるみ
過敏性腸症候群の症状 - SYMPTOMS
腹痛や便通異常、膨満感などの腹部症状だけでなく、不眠や頭痛などを起こすこともあります。
- 腹部症状
腹痛、下痢、便秘、残便感、膨満感、おなかが鳴る、不意にガスが漏れるなど
- 腹部以外に生じる症状
不眠、不安感、抑うつ、頭痛、めまい、肩こり、食欲不振など
過敏性腸症候群の診断

過敏性腸症候群では、大腸粘膜の炎症など器質的な問題はありません。ただし、過敏性腸症候群で生じる症状の多くは、他の大腸疾患とも共通していますので、大腸カメラで大腸粘膜の状態を観察し、異常がないことを確認する必要があります。特に早急な治療が必要な炎症性大腸疾患や大腸がんではないことを確かめることが重要なために大腸カメラに加え血液検査なども行います。
他の疾患ではないことが確認されたら、改めて丁寧な問診を行います。そこでは、症状が起こりはじめた時期や頻度、症状の変化、便の状態、排便回数、症状を起こすきっかけ、食事などを含む生活習慣、ライフスタイル、病歴や服用している薬などについて伺い、過敏性腸症候群の世界的な診断基準であるRomeⅣ基準をもとに診断しています。
RomeⅣ基準
過去3か月間の症状を確認し、下記の項目の2つ以上が当てはまり、月に3日以上に渡って繰り返し症状を起こしていると医師が判断した場合に診断されます。
- 排便により症状が緩和する
- 症状とともに排便回数の増減がある
- 症状とともに便の形状変化がある
※便の形状変化とは、水のような下痢、ウサギの糞のように小さくて丸くコロコロした便などを指します。
過敏性腸症候群の治療 - TREATMENT
つらい症状を薬物療法で緩和させ、生活習慣を見直します。
生活習慣の改善とストレスの上手な解消は、症状の緩和と解消、再発防止にも有効です。
- 生活習慣の改善
食事
- 3食をできるだけ同じ時間にとる
- 食物繊維と水分をしっかりとる
- 暴飲暴食を避ける
- 栄養バランスを考えた食事をとる
- 刺激が強い香辛料・カフェイン・アルコールを過剰にとらない
休息と睡眠をしっかりとる
- やや早足の散歩など軽い有酸素運動を習慣付ける
- 夏も毎日バスタブに浸かり、身体をしっかり温める
- 入浴後は身体を冷やさないよう心がける
- 趣味やスポーツなど、熱中できる時間を積極的につくる
- 浴室・トイレ・寝室などをリラックスできる空間にする
- 薬物療法
過敏性腸症候群は様々な症状を起こす疾患であり、患者さんがお悩みになっている症状もそれぞれ異なります。使用される薬は、消化管機能を改善するもの、便の水分量を整えるもの、下痢や便秘の症状を緩和させるものなどがあり、新しい作用を持った薬も登場しています。また、同じ作用の薬でも効果の現れ方、服用間隔などが違うものがありますので、当院では、患者さんの状態やお悩み、ライフスタイルなどにきめ細かく合わせた処方を行っています。下痢型の症状でお悩みの方には、予兆を感じた時に服用してその後に現れる症状を軽くする薬を処方することもあります。乳酸菌などのプロバイオティクス、漢方薬などが使われることもあります。
症状の変化によって有効な処方が変わってくる場合もありますので、再診時には処方を微調整し、より効果の高い処方になるようにしています。
焦らずに治療しましょう

過敏性腸症候群は慢性疾患であり、じっくり治すことが重要です。症状が落ち着くまでに短くて数か月、長くなると年単位の期間がかかります。さらに、症状が落ち着いても、再発することがありますので焦らずに治療に取り組む必要があります。当院では、できるだけストレスなく治療を続けられるようしっかりサポートしていますので、些細なことでも遠慮なくご相談ください。

当院では各務原市はもちろんですが、岐阜市、岐南町、関市、笠松町、羽島市、瑞穂市にお住いの方からも過敏性腸症候群などの消化器症状の診察・治療目的でご来院して頂いております。
当院は、経験豊かな消化器内視鏡専門医が診察を行っております。過敏性腸症候群などの消化器症状でお困りの方はお気軽に当院へご相談ください。
また、当院は国道156号線沿いに位置しており、本巣市、山県市、美濃加茂市、美濃市、郡上市、一宮市、江南市、犬山市、扶桑町、大口町からのアクセスも良いため多くの患者様にご来院いただいております。

文責:東海内科・内視鏡クリニック岐阜各務原院 院長 神谷友康