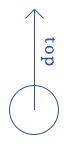当院では、消化器内科として肝疾患(肝機能障害)や膵疾患、胆嚢などの病気について診療を行っています。肝臓の病気としては脂肪肝やウイルス性肝炎、肝硬変、アルコール性肝炎、自己免疫性肝炎などの肝臓の病気について診療を行っています。また慢性膵炎や胆石症、胆嚢ポリープなどの診療も行っています。
下記のような方は当院にご相談ください。
- 健康診断で肝機能障害を指摘された
- 最近疲れやすい
- だるい、食欲がない
- 黄疸(眼の色や皮膚が黄色い)がでている
肝臓は沈黙の臓器と呼ばれ、病気ができても痛みなどの症状がでません。したがって、病気にかかっても重篤になるまで気づかずに放置をされてしまうとがあります。早期発見早期治療と、しっかりと定期的に経過を観察することが重要です。
必要に応じて近隣の病院と連携を図り、高度な検査や治療を受けるための紹介も行っています。
目次
肝機能異常を指摘されたらご相談ください
 健康診断や人間ドックで「肝機能異常」「要検査」と指摘されましたら当院までご相談ください。
健康診断や人間ドックで「肝機能異常」「要検査」と指摘されましたら当院までご相談ください。
精密検査を受けることで、肝臓がどのような状態にあるのか確認できます。また、肝臓の精密検査として腹部エコー検査を受けることで、肝臓だけでなく腎臓など他の腹部臓器の状態も確認できます。
当院で可能な肝臓の検査
- 血液検査(肝機能・ウイルスマーカー)
AST、ALT、γ-GTP、ALP、総ビリルビン、LDHなどの肝機能項目に加え、B型・C型肝炎ウイルス(HBs抗原、HCV抗体)などもチェックできます。定期健診や疲労感が続く方、健診異常の精査にも対応します。
- 腫瘍マーカー(AFP・PIVKA-II)
肝細胞がんの早期発見に重要な腫瘍マーカー検査も行っています。慢性肝炎や肝硬変がある方には定期的な測定を推奨しています。
- 腹部エコー検査(超音波検査)
肝臓の大きさ、脂肪沈着、腫瘍や嚢胞の有無、胆のう・胆管・脾臓まで一度に観察できます。痛みもなく、被ばくのない検査で脂肪肝や肝腫瘤のスクリーニングに最適です。
- CT検査(予約不要)
腹部CT検査にて胆管や肝臓周囲の異常、肝形態に異常がないかを検査することが可能です
- その他:自己免疫性肝疾患や薬剤性肝障害の評価
必要に応じて、抗核抗体、IgG、肝炎ウイルス除外検査などを組み合わせて、原因精査を行います。
肝臓の働き
肝臓は人体の工場と呼ばれ、人間が生きていく上で不可欠な臓器です。人体の中でも最大の臓器であり、腹部の右上に位置しています。アルコールや薬物の分解から、体内のタンパク質の合成、栄養素を利用可能な形に変換したり、エネルギーを貯蔵したりなど、働きは多岐にわたります。肝臓は数千の酵素を使用し、500以上の化学反応を同時に起こす能力を持っていると言われています。
- 肝臓の代謝
消化管で吸収された食べ物は肝臓に運ばれ、栄養素が代謝されます。代謝された栄養素は血液中に放出されるか、肝臓に蓄えられます。糖尿病や脂質異常症などの代謝疾患の治療には、肝臓の機能を理解することが重要です。肝臓は血液中の余分な糖をグリコーゲンとして蓄え、必要な時に放出して血糖値を調整します。また、体内のコレステロールの70%は肝臓で生成され、高コレステロール血症の治療は肝臓をターゲットにします。さらに、重要なタンパク質であるアルブミンや凝固因子も肝臓で合成され、血液中に放出されます。
- 解毒
肝臓は私たちが摂取したアルコールや薬物、代謝産物などの有害物質を無毒化し、尿や胆汁として排泄する解毒作用を持っています。また、タンパク質やアミノ酸の分解によって生成されるアンモニアも肝臓で尿素に変換され、尿中に排出されます。
- 胆汁の生成
肝臓は胆汁の生成も行っており、脂肪の消化・吸収を助けます。肝臓で生成された胆汁は胆管に分泌され、胆嚢で濃縮された後、十二指腸で膵液と共に脂肪の分解を助けます。
肝臓内科の病気
ウイルス性肝炎
ウイルス性肝炎は、A型・B型・C型などのウイルスが原因で肝臓に炎症を起こす病気です。特にB型・C型は慢性化すると肝硬変や肝がんの原因になることがあり、早期発見と定期的な検査が重要です。C型肝炎は現在では飲み薬で治療・完治が可能です。感染経路や治療法はウイルスの種類によって異なるため、医療機関での正確な診断と管理が大切です。
脂肪肝・NASH
脂肪肝は、肝臓に中性脂肪がたまりすぎた状態で、飲酒が原因でないものを「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」と呼びます。その中でも、炎症や線維化が進行したタイプがNASH(非アルコール性脂肪性肝炎)です。NASHは進行すると肝硬変や肝がんのリスクがあり、放置は危険です。肥満、糖尿病、脂質異常症などが原因となるため、生活習慣の改善が最も重要な治療です。
アルコール性肝障害
アルコール性肝障害は、長期間の過剰な飲酒によって肝臓にダメージが蓄積し、脂肪肝・肝炎・肝硬変へと進行する病気です。初期の「アルコール性脂肪肝」は自覚症状がなく、飲酒を続けることで「アルコール性肝炎」や「肝硬変」に移行することがあります。禁酒が治療の基本であり、早期に生活習慣を見直すことで進行を防ぐことができます。定期的な肝機能検査と専門的なフォローが大切です。
自己免疫性肝炎
自己免疫性肝炎(AIH)は、体の免疫システムが誤って自分の肝臓を攻撃してしまう病気です。原因ははっきりわかっていませんが、中高年の女性に多く見られます。進行すると肝硬変に至ることもあるため、早期発見と治療が重要です。治療にはステロイドなどの免疫抑制剤を使用し、炎症を抑えることで病状の安定を図ります。血液検査や肝生検で診断され、定期的な経過観察が必要です。
原発性胆汁性胆管炎
原発性胆汁性胆管炎(PBC)は、肝臓内の細い胆管が少しずつ破壊されていく自己免疫性の慢性肝疾患です。胆汁が流れにくくなり、肝臓に炎症や線維化を引き起こします。初期には自覚症状がないことも多いですが、かゆみや倦怠感、脂質異常などがみられることがあります。進行すると肝硬変に至るため、ウルソデオキシコール酸(UDCA)などの内服治療と定期的な検査が重要です。女性に多く、早期診断が予後に大きく影響します。
肝嚢胞
肝嚢胞(かんのうほう)は、肝臓にできる液体の入った袋状の構造で、多くは良性で無症状のまま発見されます。健康診断や腹部エコー、CT検査で偶然見つかることがほとんどです。嚢胞が小さい場合は治療の必要はなく、定期的な経過観察で十分です。ただし、まれに嚢胞が大きくなって腹部の圧迫感や痛みを引き起こすことがあり、その場合は治療(穿刺や手術)が検討されます。悪性化することは非常にまれです。
肝血管腫
肝血管腫(かんけっかんしゅ)は、肝臓にできる良性の腫瘍で、最も頻度の高い肝腫瘍のひとつです。血管が集まってできた塊で、通常は無症状で、健康診断や画像検査(エコー・CT・MRI)で偶然発見されます。
ほとんどの場合は経過観察のみで治療は不要ですが、まれに腫瘍が大きくなって腹部の違和感や圧迫感を感じることもあります。悪性化することは極めてまれで、安心して経過を見ることができます。定期的な画像検査によるフォローが推奨されます。
肝細胞癌
肝細胞癌(かんさいぼうがん)は、肝臓にできる最も代表的な原発性肝がんで、多くは慢性肝炎(B型・C型)や肝硬変を背景に発症します。初期には自覚症状がほとんどなく、進行するにつれて体重減少、倦怠感、腹部の張りや痛みなどが現れることがあります。
治療は、腫瘍の大きさ・数・肝機能の程度によって異なり、外科的切除、ラジオ波焼灼(RFA)、肝動脈塞栓療法(TACE)、分子標的薬、免疫療法などが選択されます。肝細胞癌は早期発見で根治が可能なため、慢性肝疾患のある方は定期的な画像検査と腫瘍マーカー(AFP、PIVKA-II)測定が重要です。
薬剤性肝障害
薬剤性肝障害は、薬や健康食品、サプリメントなどの成分が原因で肝臓に炎症や障害を引き起こす病気です。抗生物質や解熱鎮痛薬、漢方薬、サプリメントなど、日常的に使われる薬でも起こる可能性があります。症状は無症状のことも多いですが、重症化すると倦怠感、黄疸、発熱、かゆみなどが現れることがあります。
原因薬剤を中止することで改善することが多いですが、まれに劇症肝炎に進行することもあるため注意が必要です。複数の薬を使用している方や、自己判断でサプリメントを摂取している方は、肝機能検査を定期的に受けることが推奨されます。
文責:東海内科・内視鏡クリニック岐阜各務原院 院長 神谷友康


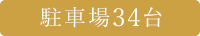
 肝臓は自覚症状が出にくく、気づかぬうちに進行することもあります。健診で肝機能異常を指摘された方や、疲れやすさが続く方は
肝臓は自覚症状が出にくく、気づかぬうちに進行することもあります。健診で肝機能異常を指摘された方や、疲れやすさが続く方は