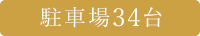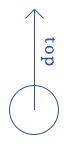血清アミラーゼが高いとは。
健康診断や日常の血液検査でアミラーゼが高いと指摘された。
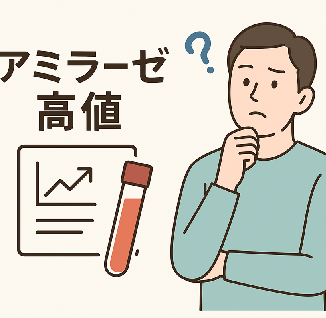 アミラーゼ(amylase)とは、主にでんぷん(糖質)を分解する酵素のことで、炭水化物の消化に欠かせない消化酵素のひとつです。人の体内では、主に唾液腺と膵臓(すいぞう)から分泌されており、それぞれ「唾液アミラーゼ」「膵アミラーゼ」と呼ばれます。
アミラーゼ(amylase)とは、主にでんぷん(糖質)を分解する酵素のことで、炭水化物の消化に欠かせない消化酵素のひとつです。人の体内では、主に唾液腺と膵臓(すいぞう)から分泌されており、それぞれ「唾液アミラーゼ」「膵アミラーゼ」と呼ばれます。
■ アミラーゼの働きと種類
- 唾液アミラーゼ(p-アミラーゼ):口の中で、食べ物中のでんぷんを分解し始めます。
- 膵アミラーゼ(s-アミラーゼ):膵液とともに小腸に分泌され、消化をさらに進めます。
アミラーゼは血液検査や尿検査で測定することができ、特に膵臓の病気である急性膵炎や慢性膵炎、膵癌の診断に重要な指標となります。
アミラーゼが高値の場合は膵臓の病気が隠れている可能性があるため医療機関を受診しましょう。
アミラーゼに異常があるときに考えられる原因と疾患
血液中のアミラーゼ値が高くなる原因には、以下のような病気があります
急性膵炎
【概要・原因】
急性膵炎は、膵臓の消化酵素が自己の膵臓を消化してしまうことで起こる急性の炎症性疾患です。 主な原因は過度の飲酒と**胆石(胆管結石)**で、その他に高脂血症、薬剤性、外傷、ERCP後などもあります。
【症状・診断】
代表的な症状は、みぞおちの激しい痛み(しばしば背部まで放散)、吐き気・嘔吐・発熱などです。 血液検査でアミラーゼ・リパーゼの上昇があり、CTや超音波で膵腫大や周囲炎症を確認します。 診断基準は「①腹痛」「②膵酵素上昇」「③画像所見」のうち2つ以上を満たすことです。
【治療方法】
治療の基本は絶食と補液による膵の安静、痛みのコントロール、必要に応じた抗菌薬や胆石除去です。 重症例では多臓器不全や壊死性膵炎、感染性合併症に注意が必要で、ICU管理となることもあります。 軽症なら数日で回復しますが、重症化すると**致死率が10〜30%**に達することもあり、早期判断と適切な治療が予後を左右します。
慢性膵炎
【概要・原因】
慢性膵炎は、膵臓に持続的な炎症が起こり、徐々に膵臓の働き(外分泌・内分泌機能)が失われていく病気です。 主な原因は長年の飲酒が最多で、その他にも胆石、遺伝、高脂血症、自己免疫、特発性などが関与します。
【症状・診断】
典型的な症状は上腹部や背部の慢性の痛み、食後の膨満感や下痢、脂肪便(白っぽい便)など。 病気が進行すると膵性糖尿病(2次性糖尿病)を発症します。
診断にはCT、MRI、超音波、膵管造影(ERCP)などの画像検査が重要で、血液検査だけでは見逃されることもあります。
【治療方法】
治療の基本は禁酒・禁煙・低脂肪食の徹底と、必要に応じた膵酵素製剤の補充です。 強い痛みがあれば、鎮痛薬や内視鏡的処置、外科的治療を行うこともあります。 慢性膵炎を長期にわたり放置すると、膵がんのリスクが高まるため、定期的なフォローアップが重要です。
耳下腺炎
【概要・原因】
耳下腺炎は、耳の前あたりにある唾液腺(耳下腺)に炎症が起こる疾患です。
原因には以下の2つのパターンがあります:
- ウイルス性(最も多い)…特に**おたふくかぜ(ムンプスウイルス)**が代表的
- 細菌性…口腔内の細菌が逆流して感染、唾液のうっ滞や脱水で起こりやすい
その他、自己免疫(シェーグレン症候群など)でも耳下腺腫脹をきたすことがあります。
【症状・診断】
耳の前〜頬の腫れ・痛みが主な症状(片側または両側) ウイルス性では発熱・倦怠感、小児では両側性が多い 細菌性では片側の強い痛み・発赤・膿性分泌がみられます 血液検査(炎症反応、ムンプスIgM抗体)や、エコー検査で膿瘍・腫大を確認します
【治療方法】
-
- ウイルス性(ムンプス):対症療法(解熱・鎮痛・安静)
→ 自然軽快するが、睾丸炎・卵巣炎・難聴などの合併症に注意
- 細菌性:抗菌薬治療+口腔内清潔・水分補給
→ 重症化や膿瘍形成例では切開排膿が必要なこともあり
通常は1〜2週間で改善しますが、合併症や再発に注意が必要です。
唾石症
唾石症とは、唾液腺(特に顎下腺)に結石(唾石)ができる疾患です。
唾石が唾液の通り道である唾液腺管(ワルトン管など)を塞ぐことで、唾液の流れが妨げられ、痛みや腫れ、炎症を引き起こします。
■ 唾石症でアミラーゼが高くなる理由
▶ アミラーゼは唾液にも含まれる
アミラーゼ(特にS型アミラーゼ)は、唾液腺(耳下腺・顎下腺など)で産生される酵素で、デンプンの消化を助ける働きをします。
唾液腺に炎症や閉塞が起こると、血中にS型アミラーゼが漏れ出すため、アミラーゼ値が上昇することがあります。
膵がん
健診で「血清アミラーゼ値が高い」と指摘された場合、多くは一過性の変化や良性疾患によるものですが、膵臓がんをはじめとする膵疾患の早期徴候である可能性も否定はできません。特に無症状の段階でアミラーゼ異常を指摘された場合、早期膵がんのスクリーニングのきっかけとなるケースもあり、放置せずに精密検査を受けることが重要です。
膵臓がんとアミラーゼ高値の関連性
膵臓がんにおいては、腫瘍による膵管狭窄や閉塞が起こることで、膵液のうっ滞や漏出を生じ、血中アミラーゼ濃度が上昇することがあります。 特に、膵がんが主膵管に及ぶ場合や、嚢胞性病変(IPMNなど)を伴う場合、軽度から中等度のアミラーゼ高値がみられることがあります。 また、膵がんの中には、無症候性の慢性膵炎を背景として進行するものもあり、健診でのアミラーゼ異常が唯一の手がかりとなることもあります。
アミラーゼが高値であるときに必要な検査
アミラーゼが高値の時は下記の検査を組み合わせ行います。
まずは膵由来のアミラーゼか唾液腺由来のアミラーゼかと判断することが大事です。
膵由来の場合は腫瘍がないか、膵炎などの炎症がないかを判断していきます。
- 血清アミラーゼ分画(P型・S型)
目的:アミラーゼが膵臓由来(P型)か唾液腺由来(S型)かを区別します。
意義:アミラーゼが高い原因が膵臓からか唾液腺からかを見極める初期スクリーニングに有用です。
- 血液検査(膵酵素・腫瘍マーカー)
リパーゼ:膵臓に特異的な酵素で、急性膵炎ではアミラーゼより感度が高いとされています。
エラスターゼ-1、トリプシン:膵実質障害を反映します。
CA19-9、DUPAN-2:膵臓がんの腫瘍マーカーとして有用です。
- 腹部超音波検査(腹部エコー)
目的:膵臓・肝臓・胆嚢・腎臓などを観察します。膵臓に腫瘤や慢性膵炎の所見がないかなどをみます。
所見:膵腫大、嚢胞、腫瘍、胆石、腎機能障害の評価を行います。
- 腹部CT検査
目的:膵臓の構造・腫瘍・炎症・壊死の評価
推奨:膵炎や膵腫瘍が疑われる場合に非常に有用です。
(膵臓がんの早期発見にも重要)
- 腹部MRI(特にMRCP)
目的:膵管や胆管の狭窄・拡張・結石・嚢胞を非侵襲的に描出します。
有効例:膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)や慢性膵炎などが疑われる際に特に有用です。
膵がんの可能性を示唆する兆候
膵がんは、早期では自覚症状がほとんどなく、気づいたときには進行していることが多い“沈黙のがん”です。 健診でたまたまアミラーゼが高く、「気のせいかもしれない」「疲れてただけかも」と様子を見るうちに、取り返しのつかないタイミングで見つかることもあります。 膵がんは、1ヶ月発見が遅れるだけで治療の選択肢が狭まると言われる非常に厄介ながんです。
特に下記のような症状の場合は注意が必要です。
- 膵由来(P型)アミラーゼが特に高い
- リパーゼも同時に上昇している
- CA19-9など腫瘍マーカーの上昇
- 腹部〜背中の違和感・鈍痛がある
- 体重減少・食欲不振・疲れやすさなどの全身症状
- 新たに糖尿病を発症、あるいは血糖コントロールが急に悪化した
- 黄疸(皮膚や白目が黄色い)や便の色の変化がある
- 膵がんの家族歴がある、喫煙歴が長い
膵がんに注意するべき人はどんな人?
膵癌のリスク要因として下記のものがあります。
〇膵癌のリスクファクター
- 家族歴: 膵癌、遺伝性膵癌症候群
- 糖尿病
- 慢性膵炎、遺伝性膵炎
- 喫煙、大量に飲酒する方
●膵がんの家族歴がある方は要注意
膵がんの家族歴がある人は、家族歴がない人と比べて、膵がんを発症する確率が1.6~3.4倍高いと言われています。
したがって定期的な健診やドックで検査を受けることをお薦めします。
まとめ
小さな“酵素の異変”が、大きな病のサインかもしれません
アミラーゼは、普段あまり意識されることのない酵素ですが、その数値の変化が、膵臓や唾液腺の異常、そして時に膵がんの兆候を映し出すことがあります。
健診で「アミラーゼが高い」と言われても、体調に問題がなければ放置してしまいがちです。
しかし、膵がんのような“沈黙の病”は、症状が出てからでは遅いこともあります。
“なんとなくの異常値”を専門医の目で確認することが、未来の安心につながります。
当院では、アミラーゼ高値に対する初期の検査・画像診断に対応しています。
不安がある方は、ご相談ください。
この記事を書いた人

神谷 友康
「医は仁術」
消化器系を中心に内科領域全般を診療しています。
医学をみなさんの日常生活でお役に立てる内容で発信したいと思っています。
資格
日本内科学会総合内科専門医、消化器内視鏡専門医、消化器病専門医など
経歴
愛知医科大学医学部医学科卒業
名古屋セントラル病院消化器内科レジデント
東海学院大学食健康学福祉部講師
名古屋セントラル病院消化器内科医長
愛知県がんセンター病院内視鏡部医長
東海内科・内視鏡クリニック 岐阜各務原院院長
参考文献
Pancreatic Adenocarcinoma, Version 2.2021, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology