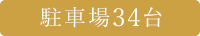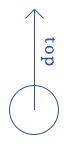慢性腎臓病(CKD)の当院の取り組み
当院では、総合内科専門医、腎臓内科専門医(水曜日午前)の医師が慢性腎臓病の診察・治療を行っています。慢性腎臓病は発症早期の段階から適切な治療を受けていただくことで、腎臓の悪化を予防し、健康な状態を維持することに繋がります。腎臓の数値が悪いなどと指摘された方は、お気軽にご相談してください。
当院では人工透析は行っておりませんので、慢性腎不全にまで進行した方は、透析療法などが可能な医療施設にご紹介させていただきます。
以下の項目に当てはまる人は要注意です

- 健診で腎臓が悪いと言われた。
- むくみが気になるようになった。
- 疲れやすくなった
- 長年、高血圧や糖尿病の治療を受けている(放置している)
- 最近、尿量が増えたような気がする
- 尿が泡立つようになった
- 夜間に頻尿になった。
上記のような項目に一つでも当てはまる方は慢性腎臓病(CKD)の可能性があります。
目次
慢性腎臓病(CKD)とは
 慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease; CKD)は、以下のいずれかの状態が3カ月以上持続する場合に診断されます。
慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease; CKD)は、以下のいずれかの状態が3カ月以上持続する場合に診断されます。
- 尿検査、血液検査、画像検査、組織検査などで腎障害が確認される
- 糸球体濾過値(GFR)が60(mL/min/1.73m²)未満
慢性腎臓病(CKD)は進行度に応じてステージが分類されます。患者さんの年齢、基礎疾患、経過によって異なるため、ステージ分類はあくまで一つの指標です。
慢性腎臓病(CKD)のステージ分類と腎機能(GFR)
慢性腎臓病(CKD)はGFR(糸球体濾過値)の低下に伴い5つのステージに分類され、ステージが進行するほど腎機能が低下し、体にさまざまな影響を及ぼします。
慢性腎臓病(CKD)の進行とGFRの関係
以下は、腎機能(GFR)と慢性腎臓病のステージを示しています。
慢性腎臓病(CKD)ステージ
| ステージ1(GFR 90以上) | 腎障害はあるものの、腎機能はほぼ正常。 |
| ステージ2(GFR 60~89) | 軽度の腎機能低下。自覚症状はほとんどなし。 |
| ステージ3(GFR 30~59) | 中等度の腎機能低下。倦怠感や夜間尿が増える。 |
| ステージ4(GFR 15~29) | 重度の腎機能低下。貧血や高血圧、むくみが目立つ。 |
| ステージ5(GFR 15未満) | 末期腎不全。透析や腎移植が必要となる。 |
このように、腎機能が低下するにつれてさまざまな症状が現れ、日常生活に影響を与えるようになります。早期発見と管理が重要です。
ステージが3以上の場合は慢性腎臓病(CKD)が疑われます。
慢性腎臓病の原因
慢性腎臓病の主な原因
大きく分けて
①生活習慣病が原因となるもの
②腎臓自体の病気によるもの
の2つがあります。
生活習慣病が原因となるもの
原因の多くは、高血圧や糖尿病などの生活習慣病が原因で起こります。
- 糖尿病(糖尿病性腎症)
血糖値が高い状態が続くと、腎臓の血管がダメージを受け、ろ過機能が低下します。日本では CKDの約40% が糖尿病が原因と言われています。 血糖コントロールをしっかり行い、腎臓に負担をかけないことが重要です。
- 高血圧(高血圧性腎硬化症)
高血圧が続くと腎臓の細かい血管が硬くなり、血流が悪くなります。腎臓に十分な酸素や栄養が行き届かず、機能が徐々に低下します。 塩分を控え、適度な運動をして血圧を管理しましょう。
- 動脈硬化(腎血管性高血圧)
動脈硬化によって腎臓の血流が悪くなり、腎臓が正常に働けなくなります。高齢者に多いタイプのCKDです。 バランスの取れた食事と生活習慣の改善が大切です。
- 肥満・メタボリックシンドローム
肥満があると、腎臓の負担が増えて機能が低下しやすくなります。特に 脂肪肝・高血圧・糖尿病が合併するとリスクが高まります。 食事の見直しと運動を習慣化しましょう。
腎臓自体の病気が原因となる慢性腎臓病CKD
もともと腎臓の病気があると、腎機能が徐々に低下し、CKDへ進行することがあります。
- 慢性糸球体腎炎(IgA腎症など)
腎臓の糸球体(血液をろ過する部分)に炎症が起こる病気です。長年気づかずに進行し、やがて腎機能が低下します。 尿検査でタンパク尿や血尿がある場合は早めに受診をしましょう。
- 腎嚢胞(多発性嚢胞腎)
腎臓に水がたまった袋(嚢胞)ができる病気 です。遺伝性のこともあり、進行すると腎不全に至ることもあります。 定期的な検査で進行をチェックしましょう。
- 尿路結石・尿路感染症の繰り返し
腎臓や尿管に結石ができると、尿の流れが悪くなり腎臓に負担がかかります。 また、繰り返す尿路感染も腎臓にダメージを与えます。水分をしっかりとり、結石を予防することが大切です。
- 薬剤性腎障害
鎮痛剤(痛み止め)や一部の抗生物質などを 長期間使いすぎると腎臓に負担がかかり、機能低下を引き起こす ことがあります。薬を自己判断で長く使わず、医師に相談しましょう。
腎機能低下による主な症状
夜間尿
夜中に何度もトイレに行きませんか?
通常、健康な腎臓は夜間に尿を濃縮し、尿量を減らします。しかし、腎機能が低下すると抗利尿ホルモンがうまく働かなくなり、夜間にトイレへ行く回数が増えます。
腎性貧血
階段を上ると息切れしやすくなりませんか?
腎臓が造血ホルモン(エリスロポエチン)を分泌できなくなると、赤血球が不足し、貧血を引き起こします。動悸や息切れ、倦怠感が主な症状です。
高血圧・むくみ
血圧が高くなったり、足がむくむことはありませんか?
腎臓が塩分を適切に排出できなくなることで、高血圧やむくみの原因となります。
腎臓の予備能力と慢性腎臓病(CKD)の進行
腎臓にはある程度の“予備能力”があり、例えば生体腎移植のドナー(提供者)は腎臓を1つ失っても、残った腎臓が十分な機能を補うことができます。
しかし、CKDではこの予備能力が徐々に失われ、腎臓が本来の働きを果たせなくなります。 特にステージ3以降では、腎臓の機能が急速に低下しやすいため、症状がなくても定期的な検査が必要です。
慢性腎臓病(CKD)の検査
慢性腎臓病(CKD)の検査には以下のものがあります。
クレアチニン(Cr)
クレアチニン(Cr)は、筋肉中のクレアチンが代謝されて生じる老廃物で、腎臓から尿中に排泄されます。
血液中のクレアチニン値は、腎機能が低下すると上昇します。
正常値(成人):男性:約0.7〜1.1 mg/dL、女性:約0.5〜0.9 mg/dL(筋肉量により個人差あり)
ただし、クレアチニン値は筋肉量に依存するため、高齢者・女性・痩せ型の人では腎機能が低くても値が正常範囲に見えることがあります。
eGFR(推算糸球体濾過量)
eGFR(estimated Glomerular Filtration Rate)は、腎臓のろ過機能を表す数値で、「1分間にどれだけの血液を腎臓がきれいにできるか(mL/分/1.73㎡)」を示します。
尿タンパク
尿蛋白検査は本来排泄されないはずのタンパク質が検出されるかどうかを見る検査です。腎臓の糸球体または尿細管の障害を示唆する重要です。
検出の意義
+(陽性) が続く場合は、慢性腎臓病(CKD)の可能性があります。
一過性の尿蛋白(発熱・運動後・脱水など)もあり、持続性の確認が必要です。
詳細についてはこちらのページもご覧ください。尿潜血
尿に血液成分(ヘモグロビン・ミオグロビン)が混じっている状態です。
肉眼的血尿(赤く見える)と顕微鏡的血尿(潜血陽性)がります。
常に異常ではないが、泌尿器疾患・腎疾患のスクリーニングとして重要。
尿潜血検査について詳しくこちらをご覧ください。尿沈渣
尿を遠心分離して、沈殿物(細胞・結晶・円柱など)を顕微鏡で観察する検査です。尿定性検査(試験紙による尿蛋白や潜血など)と組み合わせて、腎・尿路系の異常の有無や部位を特定する補助診断として非常に有用です。
腎エコー(腹部超音波)
腹部エコー検査(超音波検査)は、腎臓・膀胱・前立腺などの泌尿器の臓器を、体に負担をかけずに調べることができる検査です。放射線を使わず、痛みもありません。
検査でわかること
- 腎臓の形や大きさ、腫瘍や嚢胞の有無
- 腎結石、水腎症(尿のつまり)
- 膀胱内の腫瘍、結石、残尿の量
- 前立腺の大きさ(前立腺肥大など)
CT検査
腎の萎縮や尿の通り道の異常を詳しく調べます
CT(コンピューター断層撮影)検査は、慢性腎臓病(CKD)の原因や進行の程度、尿の通り道の異常を確認するために重要な画像検査です。特に腎臓の萎縮や腎後性腎不全(尿路閉塞による腎機能障害)の評価に有効です。
慢性腎臓病(CKD)の進行を防ぐために
生活習慣の改善
慢性腎臓病の進行を防ぐには、以下のような生活習慣の改善が不可欠です。
- 塩分の摂取制限
高血圧を防ぐため、1日6g未満を目安に塩分摂取を控える。 - タンパク質の適切な摂取
過剰摂取を避け、医師の指導のもと適量の摂取を心がけましょう。 - 適度な運動
適度な運動は血流を促進し、腎機能の維持を助けます。 - 禁煙
血管への負担を減らし、腎臓の健康を守ります。禁煙を行いましょう。 - 定期的な検査
早期発見・早期治療が進行抑制につながる。
原因疾患の治療
慢性腎臓病の進行を防ぐには、高血圧、糖尿病、腎炎などの継続的な治療が不可欠です。
- 糖尿病、高血圧症などの生活習慣病
生活習慣の改善に加えて投薬治療が必要となる可能性があります。特に慢性腎臓病となっている方はこれ以上腎機能を悪化させないためにも厳密な治療が必要となります。高血圧や糖尿病治療薬の中には慢性腎臓病の悪化を防ぐ薬もあります。 - 腎炎など
専門医による診療が望ましいです。ステロイド製剤など病態に応じた治療が行われます。
慢性腎臓病(CKD)と心血管疾患の関係
慢性腎臓病(CKD)が進行すると、心臓や血管の疾患のリスクが高まることが知られています。適切な管理を行い、腎臓と心臓の健康を維持しましょう。 定期的な検査と医師の指導のもと、生活習慣を見直し、腎機能を守ることが大切です。
お問い合わせ
東海内科・内視鏡クリニックでは地域の皆様の健康に貢献するため、内科・婦人科診療をおこなっています。
慢性腎臓病という疾患は悪化することで人工透析が必要になるなど、重篤な状態になる可能性がある病気です。また心筋梗塞や脳梗塞などの心血管疾患のリスクも上昇します。腎機能がまださほど悪くない状態から治療を開始することが重要です。当院では腎臓内科専門医(水曜日午前)による診療を行っています。治療を希望される方はお気軽に当院へご相談ください

当院では各務原市はもちろんですが、岐阜市、岐南町、関市、笠松町、羽島市、瑞穂市にお住いの方からも診察や腎疾患の治療を目的にご来院して頂いております。
当院は、地域の皆様のご健康に貢献していくため、慢性腎臓病の治療にも力を入れております。少しでも気になる症状がある方、腎機能の数値が高い方はお気軽に当院へご相談ください。
また、当院は国道156号線沿いに位置しており、本巣市、山県市、美濃加茂市、美濃市、郡上市、一宮市、江南市、犬山市、扶桑町、大口町からのアクセスも良いため多くの患者様にご来院いただいております。

文責:東海内科・内視鏡クリニック岐阜各務原院 院長 神谷友康
参考文献:診療ガイドライン-医療従事者のみなさまへ-一般社団法人 日本腎臓学会|Japanese Society of Nephrology