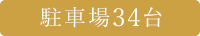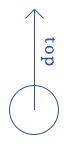こんにちは。東海内科・内視鏡クリニック院長の神谷です。
今回は、糖尿病の診断や治療でよく使われる「HbA1c」についてご説明します。
「HbA1cって何を表しているの?」「血糖値とどう違うの?」と疑問を持たれている方も多いと思います。糖尿病診療においてHbA1cは非常に重要な指標ですので、ぜひ正しく理解していただければと思います。
HbA1cとは何か?
HbA1cは「ヘモグロビンエーワンシー」と読みます。
赤血球の中にあるヘモグロビン(酸素を運ぶたんぱく質)に、血液中のブドウ糖が結合したものを指します。
赤血球はおよそ120日(約4か月)の寿命があります。そのため、HbA1cの数値は過去1~2か月間の平均血糖値を反映していると考えられています。
つまり、HbA1cは「その時の血糖値」ではなく、「最近の血糖コントロールの状態」を評価できる指標なのです。
HbA1cと血糖値の違い
血糖値:測定したその瞬間の値
HbA1c:過去1~2か月の平均的な血糖状態を反映
例えば、血糖値が食事前後で大きく変動しても、HbA1cはその平均値を示すため、日々の血糖コントロールを安定的に評価できます。
糖尿病診断とHbA1cの基準値
日本糖尿病学会の診断基準では、以下のように定められています。
HbA1c 6.5%以上 :糖尿病型
HbA1c 6.0〜6.4% :糖尿病予備群(境界型)
HbA1c 5.9%以下 :正常範囲
※診断はHbA1c単独では行わず、血糖値の検査や臨床症状とあわせて総合的に判断します。
HbA1Cはいくつ以上だと危ない?
HbA1cの数値は、単なる診断の目安にとどまらず、将来の健康を左右する重要な予後予測因子です。
特に一定値を超えた状態を長期間放置すると、全身の血管に取り返しのつかないダメージが蓄積し、糖尿病に特有の合併症だけでなく、命に関わる病気の引き金にもなります。
危険性は「ある/ない」の二分法ではなく、数値が高くなるほど、またその状態が続くほど、リスクは雪だるま式に増加していくという「量依存的」な性質を持つことを理解しておくことが大切です。
危険レベル1:HbA1c 7.0% ~ 合併症予防の境界ライン
日本糖尿病学会が目標として掲げる「HbA1c 7.0%未満」。
この値は、糖尿病治療における最も重要な「防波堤」と考えるべき数値です。
7%を超えると、まず細い血管(細小血管)が障害を受け始め、糖尿病の代表的な3大合併症が進行しやすくなります。
- 糖尿病網膜症 :視力低下から失明へ進行するリスク
- 糖尿病腎症 :腎機能低下から透析導入へつながる危険
- 糖尿病神経障害:手足のしびれ・痛み、壊疽や切断のリスク
HbA1cが7%台にある状態は、すでに合併症の扉が開き始めている段階であり、ここでの治療介入が将来を大きく左右します。
危険レベル2:HbA1c 8.0%以上 ~ 合併症の進行加速期
8%を超えると、合併症は「予防段階」から「進行段階」へ移行します。
- 5年以内 :末梢神経障害によるしびれや感覚鈍麻
- 7~10年後 :網膜症の悪化により失明の危機
- 10年以上 :腎症の進行により透析導入が必要になるケースが増加(日本では年間1万4千人以上が新規透析導入)
さらにこの段階では、心筋梗塞や脳梗塞といった「大血管障害」リスクも急増し、突然死の危険も現実的になります。
危険レベル3:HbA1c 9.0%以上 ~ 全身の危機的状態
HbA1cが9%を超えると、全身が深刻な代謝異常の状態にあります。倦怠感や強い疲労感などの症状が現れやすくなり、場合によっては入院治療が必要になることもあります。
この段階でのリスクは、血管合併症にとどまりません。
感染症リスク:免疫低下により肺炎・尿路感染症・皮膚感染症などを発症しやすく、重症化もしやすい
がんのリスク:高血糖状態が続くことで発がんリスクが1.2~1.3倍に上昇すると報告されている
糖尿病性ケトアシドーシス:命を脅かす急性合併症。血液が酸性に傾き、昏睡や死亡に至る危険性も
HbA1cが9%以上というのは、「合併症が進むリスク」ではなく、すでに命に直結する危険領域であることを意味します。
HbA1Cはどれぐらいを目指すといい?
成人における血糖コントロール目標(日本糖尿病学会)
日本糖尿病学会では、成人糖尿病患者さんの血糖コントロールについて、患者さんの状態や治療環境に応じて 3つの目標レベルを設定しています。
合併症予防を目的とした目標(HbA1c < 7.0%)
最も基本的で広く推奨される目標です。多くの成人糖尿病患者さんに適用され、細小血管合併症(網膜症・腎症・神経障害)を予防する効果が臨床研究で明らかになっています。
目安としては、
空腹時血糖値:130mg/dL未満
食後2時間血糖値:180mg/dL未満
が、おおよその基準とされています。
正常化を目指す目標(HbA1c < 6.0%)
さらに厳密なコントロールを目指す場合の基準です。
対象となるのは、比較的若年で糖尿病の罹病期間が短く、食事・運動療法や低血糖リスクの少ない薬剤のみで達成可能な患者さんです。
このレベルのコントロールが実現すれば、将来的な心血管疾患リスクの低減につながる可能性が示されています。
治療強化が難しい場合の目標(HbA1c < 8.0%)
一律に厳格なコントロールを目指すことが必ずしも最善とは限りません。
高齢者や、重度の合併症を持つ方、低血糖を繰り返す方などでは、HbA1cを7.0%未満に抑えることがかえって危険につながる場合があります。
こうしたケースでは、安全性と生活の質(QOL)を優先し、8.0%未満を目標とすることが推奨されています。
これは「妥協」ではなく、その人に合った最適な治療目標を設定していると理解することが大切です。
HbA1cを下げるための生活改善ポイント
1. 食事療法
主食(ごはん・パン・麺類)は食べ過ぎに注意
野菜を先に食べる「ベジファースト」で血糖の上昇を緩やかに
甘い飲み物・お菓子を控える
適度なたんぱく質(魚・大豆・鶏肉)をバランスよく摂取
2. 運動療法
1日30分程度のウォーキングや軽い筋トレを継続
食後30分以内の軽い運動が特に有効
3. 体重管理
内臓脂肪を減らすことでインスリンの働きが改善
BMI(体格指数)25未満を目標に
4. 薬物療法
生活習慣の改善だけで不十分な場合には、糖尿病薬を併用します。最近ではGLP-1受容体作動薬やSGLT2阻害薬など、新しい作用機序の薬もあり、患者さんごとに最適な治療を組み合わせます。
HbA1c改善のために大切なこと
HbA1cは「長期的な血糖管理の通信簿」とも言える数値です。
一度下がっても油断するとすぐに上昇してしまうため、継続した生活習慣の改善と、定期的な通院が重要です。
糖尿病は自覚症状が少なくても、合併症(網膜症・腎症・神経障害、心筋梗塞や脳梗塞)につながる恐れがあります。HbA1cをしっかりコントロールして、健康寿命を延ばしていきましょう。
まとめ
HbA1cは過去1〜2か月の平均血糖値を反映する指標
糖尿病診断の基準値は6.5%以上
改善のためには食事・運動・体重管理・薬物療法を組み合わせることが大切
定期的なチェックと継続的な取り組みが不可欠
当院では、糖尿病の診断・治療だけでなく、生活習慣の具体的なアドバイスやお薬の調整も行っています。
「HbA1cが高いと言われた」「数値がなかなか下がらない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
この記事を書いた人

神谷 友康
「医は仁術」
消化器系を中心に内科領域全般を診療しています。
医学をみなさんの日常生活でお役に立てる内容で発信したいと思っています。
資格
日本内科学会総合内科専門医、消化器内視鏡専門医、消化器病専門医など
経歴
愛知医科大学医学部医学科卒業
名古屋セントラル病院消化器内科レジデント
東海学院大学食健康学福祉部講師
名古屋セントラル病院消化器内科医長
愛知県がんセンター病院内視鏡部医長
東海内科・内視鏡クリニック 岐阜各務原院院長
参考文献